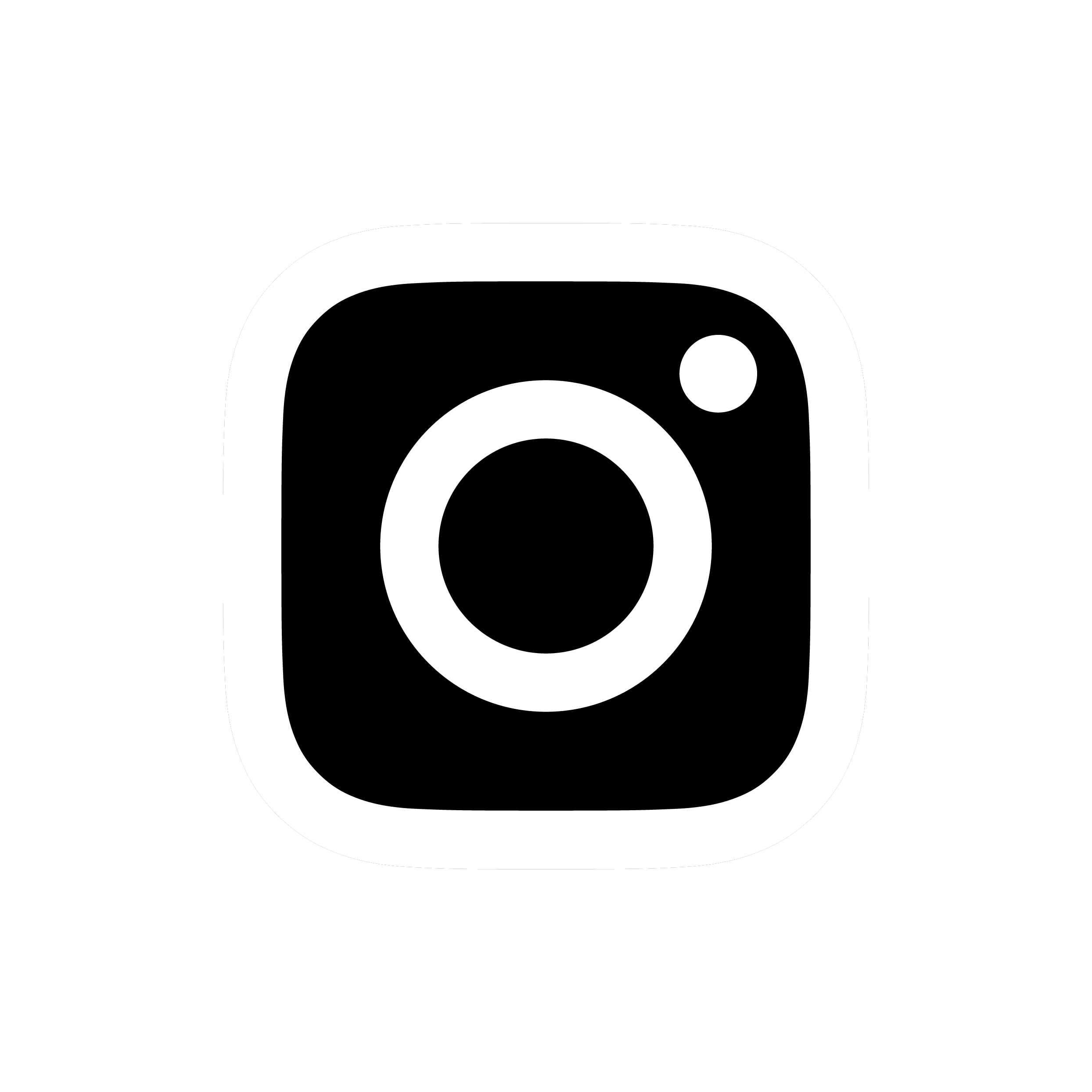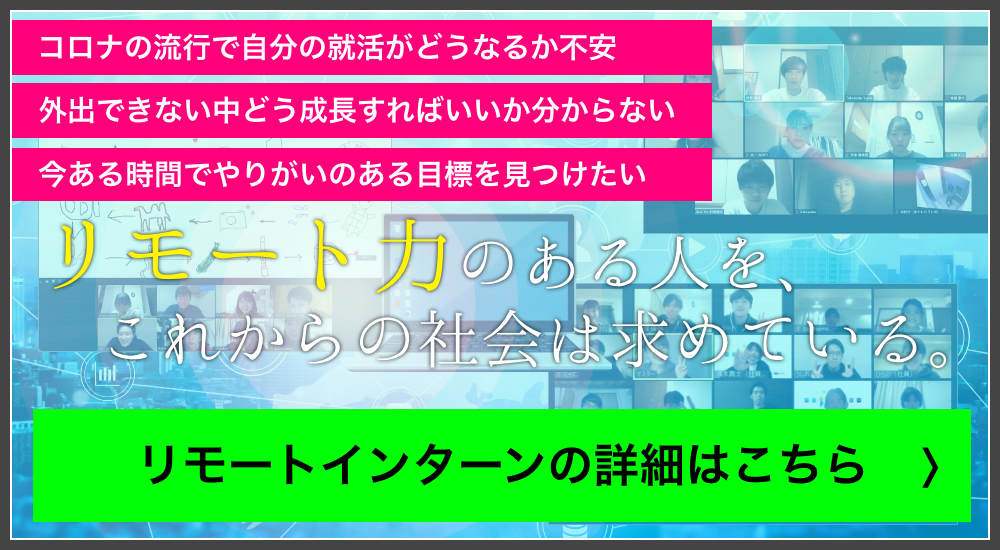みなさんこんにちは
つい最近20歳の誕生日を迎えました、京都大学経済学部1回生の西留です。
未来電子では現在マーケティングチームに所属しており、ライター、アナリスト、マネージャー業務を行っています。
突然ですが、僕は小さい頃からいわゆる「完璧主義」で、一度手をつけたら自分が完璧だと思えるまでとことんやりぬかずにはいられませんでした。
そんな僕にとって、「完璧主義」というのはあまりいいものではなく、ずっとなおしたいと思っていたものでした。(理由は後述します。)
今回は、未来電子に入社してからの約5ヶ月間での僕の「完璧主義」に対する考え方の変化についてみなさんにシェアしたいと思います。
□小さい頃から「完璧主義」だった
小さい頃から続く僕の「完璧主義」は、「心配性」の延長にあるものです。
心配性であるがゆえに、「これはこのままで大丈夫だろうか」と何度も見直し、考え直しをして、心配がなくなるまで(=「完璧」と思えるまで)やりぬかないと気が済まないのです。
そんな僕の小さい頃の「完璧主義」を象徴しているのが、小学校時代、原稿用紙2枚分のオリジナルの物語を書くという課題を課された時のエピソードです。
当時の自分は、お世辞にも文学的センスがあるとは言えなかったため、オリジナルの物語を書くことは容易ではなく、その課題をやりたくなくて憂鬱であったのを覚えています。
しかし、一度手をつけてからは、自分の中で「完璧」だと思えるまでやり抜こうと思い、最終的には原稿用紙20枚ほどの物語を書き上げました。
その完成度の高さは、客観的に見れば決して高くはなかったと思いますが、少なくとも自分の中では完璧だと思えるまで徹夜してやりこんだのを覚えています。
また、受験生時代も、例えば数学のI問を完璧に理解するために半日使ったり、英語の文法一つを理解するために2〜3時間かけたりといったこともしていました。
このように、自分が納得できる「完璧」を追い求める僕の性格は、小さい頃からずっとあるものでした。
□「完璧主義」であることによる弊害
「完璧主義」であることによって生じる深刻な問題があります。
それは、「時間が足りなくなってしまうこと」です。
上記で小学校時代の作文課題の例を挙げましたが、実はあの原稿用紙20枚にわたる作文を提出したのも、期限よりも1日遅れていました。
受験生時代も、結局自分の予定していたことを全て終わらせることはできずに試験本番に臨んでいます。
僕が未来電子に入ってからも、この「完璧主義」は業務に大きく影響しました。
未来電子に入社して最初に行う業務はライターとして記事を書くことでした。
ライターは、1時間あたり1000文字書けるようになれば、ひとまず一人前とされます。(もちろんもっと速い人はたくさんいます。)
しかし僕は例のごとく、記事を書く際にも何度も見直し、調べ直し、書き直し、ということを繰り返していた結果、2週間ほど経っても、1時間あたり平均700文字程度しか書けず、達成シートは赤字だらけでした。(その日の計画ポイントを達成できなかったら赤字になります。)
その月は夏休み中だったこともあり、なんとか時間をかけてその月の目標ポイントを達成することはできました。
しかし、次の月からは後期の授業が始まるということで、
「この状況をなんとかしなければ目標達成できなくなる…」と危機感を感じました。
□「完璧主義」はよくないことなのか
いくら「完璧」を追い求め、質を高くしても、与えられた量をこなせず、目標達成ができなければ意味がありません。
そこで、目標達成するには何を変えればいいのかを考えていた僕は、
自分が、「目の前のものを『完璧』にすることに気を取られるあまりに、長期的な目標を見失っている」ことに気がつきました。
つまり、「完璧主義」であることが悪いのではなく、悪いのは「綿密な計画が立てられていないこと」「その計画に沿って行動していないこと」だったのです。
だからこそ、重要なのは、質を追い求めつつも、より長期的な目標を見据え、綿密な計画を立てて、与えられた時間の中でできる限り「完璧」に近いものを目指していくことであるという結論に至りました。
それを実践し続けた結果、未来電子に入ってからこれまで、「毎月目標達成」かつ「リライト(記事の質が低いことによる書き直し)件数0」を達成しています。
みなさんの中にも、「完璧主義」で悩んでいる方もいらっしゃるかもしれませんが、「完璧主義」それ自体は悪いことではありません。
最終的な目標達成に向けて綿密に組んだ計画の中で「完璧主義」を実践していくことが、成果を残すために重要なのです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。